仮想通貨の確定申告で所得から差し引き出来る控除は?

-

-
仮想通貨ですが確定申告時にウォレットに移動している通貨は対象...
現在は仮想通貨購入後にウォレットに入れておりますが日本円やドルなどのお金には交換した事はございません。ただし持っている通...
-

-
XRPが堅調な上昇・リップルが上昇した幾つかの理由
20日に仮想通貨相場は全体的に堅調な推移をしました。ビットコインが90万円を超え、アルトコインは5%以上上昇している銘柄...
-

-
仮想通貨は盗まれる!?4つの盗られない対策
記憶に新しいのはコインチェックのネム流出事件です。この事件では明らかな取引所の不手際が問題でした。どんなセキュリティーで...
-

-
仮想通貨の確定申告はいくら以上(金額)行えば良いのでしょうか...
現在はサラリーマンですが今後の為に個人事業、法人に関してもお聞き出来ればと思います。申告後はいつ支払う必要があるのでしょ...
-

-
去年の仮想通貨の税金を支払ってないのに気がつきました今から支...
と思いますが税金は雑所得と決まる前なので払わなくて大丈夫なのでしょうか?雑所得となる今年では無くその前の年の税金となりま...
-

-
ビットコイン初心者が投資を始める方法
今話題のビットコインに投資したいけど始め方が分からない…ネットで調べてもビットコインの投資方法はたくさんあって迷ってしま...
-

-
中東地域においてブロックチェーン技術が加速・ブートキャンプ・...
仮想通貨やブロックチェーン技術について、規制やコメントが発表している中で、中東地域では加速する流れが出てきています。中東...
-

-
ザイフトークンの特徴と今後の将来性
国内仮想通貨取引所であるザイフ(Zaif)が取り扱っている仮想通貨の中でザイフトークンと言うのを聞きます。ザイフトークン...
-

-
透明性がある仮想通貨Stellar「ステラ」「XLM」とは
ステラはリップルの初期開発メンバーで、マウントゴックスの創設者であるジェド・マケーレブ氏が中心となって開発され、コンピュ...
-

-
中国やシンガポール等のアジアでブロックチェーン技術が加速
アジアでブロックチェーン技術が加速 アジアの様々な地域でブロックチェーン技術が加速しています。現在、注...
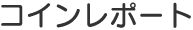
その他、控除が出来る内容を教えてください。住宅ローンなどの他に控除可能なものを教えてほしいです。あればあるだけ良いので複数ある場合は全て教えてほしいです。内容も個々に細かくお願い致します。控除が出来ない場合は理由なども教えてもらえますか?
住宅ローン控除以外に、確定申告で所得から差し引きしてもらえる控除には以下のようなものがあります。
■配偶者控除
収入がない配偶者(妻や夫)を扶養している人は、配偶者控除として38万円を所得から差し引きしてもらえます。
配偶者控除を適用してもらうためには、勤務先の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります(年の初めや、入社時に提出しているはずです)
個人事業主の人は、確定申告書類に「配偶者がいる」という欄にチェックすればOKですので、この書類を作成する必要がありません。
■扶養控除
収入のない家族を扶養している人は、扶養控除として一人につき38万円を所得から差し引きしてもらえます。
扶養控除の適用をしてもらえる家族の条件は以下の通りです。
なお、16歳未満の子供は扶養控除に含まれませんので注意してください。
■医療費控除
医療費を年間で10万円以上支出している人は医療費控除を適用してもらえます。病院の領収書が必要になりますのでそのつど保管しておきましょう。
医療費控除の計算式は以下の通りです。医療費控除の金額=支払った医療費の金額-受け取った医療保険金などの金額-10万円
■社会保険料控除
健康保険や厚生年金、国民健康保険や国民年金といった社会保険料を支払った場合、その保険料の全額を社会保険料控除として所得から差し引きしてもらえます。
サラリーマンの方であれば、社会保険料は毎月のお給料から天引きされていますので、勤務先から受け取る源泉徴収票に年間の合計保険料額が記載されています。
■生命保険料控除
生命保険に加入して保険料を払っている人は、年間で最大12万円を所得から差し引きしてもらえます。
なお、生命保険料控除には「一般の生命保険(死亡保険など)」、「介護、医療に関する生命保険」「老後保障のための生命保険」の3種類があり、控除額はそれぞれ4万円ずつとなります(合計12万円)
生命保険料控除を適用してもらうためには、保険会社が発行してくれる控除証明書が必要になります(毎年10月~11月ごろに自宅に郵送されてきます)
■地震保険料控除
地震保険に加入していて保険料を支払っている人は、年間最大5万円を所得から控除してもらえます。地震保険料控除を適用してもらうためには、生命保険料控除と同様に保険会社から郵送される控除証明書が必要になります。
■寄附金控除
公的な組織に対して寄付をした人は、寄付金控除として所得から一定額を差し引きしてもらうことができます。上でいう「公的な組織」に該当するのは、国や地方公共団体、政党や一定の公益法人などです。
寄付金控除として差し引きしてもらえる金額は、次の計算式で計算します。寄付金控除=寄付金の支出額合計-2000円
■雑損控除
災害や盗難にあった人は雑損控除として一定額を所得から控除してもらえます。
雑損控除は次で計算したいずれか多い方の金額です。
■障害者控除
国から一定の障害者として認定されている人は、障害者控除として27万円~75万円を控除してもらえます。
■小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済は、個人事業主にとっての退職金を準備するための保険です(積み立てタイプの個人年金保険のようなものです)
この小規模企業共済に加入している人は、支払った保険料全額をその年の所得から控除してもらえます。なお、小規模企業共済の保険料年額の上限は84万円です。
■寡婦(寡夫)控除
寡婦(寡夫)に該当する人は、寡夫控除として所得から27万円を控除してもらえます。
■勤労学生控除
給与所得のある学生は勤労学生控除として27万円を所得から控除してもらえます。なお、年間の合計所得が65万円以下であることが条件になります。
■配偶者特別控除
上で説明させていただいた配偶者控除が年間所得額が38万円以内のときに適用してもらえます。逆に言うと所得が38万円を超える場合には配偶者控除の適用を受けることはできないということですが、所得額が38万円超~76万円までの範囲内である場合には、金額に応じて38ま年~3万円を所得から控除してもらえます。