仮想通貨の税金は本当に「雑所得・高税率」なのかレポート

(2)「仮想通貨=高税率」なのか
仮に、仮想通貨の売却益が雑所得と認定されたとして、それは果たして本当に「高税率」を意味するのでしょうか。この点で、「一時所得」や上場株式の譲渡益と比較する必要があります。まず、「一時所得」とは、たとえば競馬の払戻金など、およそ職業的になされるものではない行為から生じる所得を言います。
この一時所得とみなされると、一回一回の売買ごとに得た利益について課税されるので、複数回の売買で何回か損失を出してしまって結果としてトータルでマイナスとなった場合でも(経費の方が収入より多い場合でも)、税金がかかってしまいます。この一時所得にあたるかどうかについて、職業的な競馬師が馬券を買う行為により得る収入は、一時所得ではなく雑所得に当たるとして、いわゆるはずれ馬券を経費として算入することを認めた最高裁判決は記憶に新しいところです。
つまり、実際の税負担としては、一般に雑所得の方が経費を算入できる点で、一時所得よりは有利なのです。他方、上場株式を売却した際の利益(譲渡益)は分離課税となります。分離課税とは、先ほど述べたような総合課税と異なり、当該所得だけで他の所得(例えば本業の給与所得や事業所得)とは別に税金が課せられる方式を言います。
つまり、株で利益が出ていれば、本業で大損を出していても税金を支払わないといけないという事態が生じてしまいます。また、税率は一律20%であり、所得の金額にかかわりなく、一定の割合の税金を支払わないといけないということになります。これに対して、雑所得は総合課税の一部です。したがって、税率は全所得ベースで決まります。あなたの所得が合計で330万円以下であれば、税率は10%で、上場株式の場合の税金より安く済むのです。
2.結論:個人が副業としてする仮想通貨の売買の税金は、その人のライフスタイルによって異なる
以上の通り、仮想通貨の売買にかかる税金が一概に高いというわけではないのです。読者の皆様におかれましては、ご自身の収入状況や仮想通貨の売買に対するスタンスを踏まえて、税金について一度考え直してみることをお勧めいたします。
弁護士 堀口 圭
*続きをお読みになる場合は閲覧キーを取得くださいませ。 *キー入力が出てる場合のみ
-

-
インドのICICI銀行が250社にブロックチェーンプラットフ...
インドの大手銀行である、ICICI銀行が17日に企業250社に対して、国内外での貿易金融取引においてブロックチェーンプラ...
-

-
資産管理サービスでもブロックチェーン普及が進む
資産管理サービスの分野でもブロックチェーンの普及が加速しています。資産と言うと預金だけに限らず、投資や不動産、さらに金な...
-

-
ビットフライヤーの手数料が高いと感じた時は3つの行動
ビットフライヤーの手数料が高いと感じる時に見直すべき箇所や行動をまとめてみました。実際は他の取引所と比べても大差はありま...
-

-
マネックスがコインチェックを買収する理由と2つの注目ポイント
今月3日、マネックス証券で知られるマネックスグループがコインチェックの買収を検討しているというニュースが日経新聞で報じら...
-

-
初めてでも大丈夫??ビットフライヤーでビットコイン購入は初心...
2017年は仮想通貨元年と呼ばれ、非常に注目を集めた仮想通貨。2018年に入り、良くも悪くも様々なニュースが飛び交ってい...
-

-
お金の洗浄!?マネーロンダリングによる事業者毎の対策は
先日、金融庁が複数の仮想通貨交換業の登録業者に対し、マネーロンダリングの不備に対して処分を行うことを発表しました。仮想通...
-

-
ロシアでも仮想通貨業界で暗号化メッセンジャーサービス「テレグ...
ロシアの通信・情報技術・マスコミ監督庁であるROSKOMNADZORが先日、仮想通貨業界で人気のある暗号化メッセンジャー...
-

-
ビットフライヤーでビットコインを上手な買い方する方法とは?
ビットフライヤーの取引口座を開設して、いさ初めての売買だ!と思ったけど上手く買えなかったり、板に記載の意...
-

-
イスラム国家において仮想通貨市場の流れ規制緩和の動き
イスラム国家において仮想通貨市場の規制緩和のような流れが出てきています。その流れについての2つの出来事についてお伝えしま...
-

-
中国開催のGlobal Fintech & Blockcha...
4月12日に中国・上海で開催されたブローチェーン・カンファレンス「Global Fintech & Blockchain...
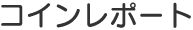
1.仮想通貨=雑所得・高税率という誤解
仮想通貨の税務について調べると、しばしば「仮想通貨は雑所得であり、税率が高い」という記載を目にすることがあります。確かに、仮想通貨の売買で得た利益は一般に雑所得に分類されることが多く、いわゆる「億り人」にとって高税率になることがあることも否めません。
しかしながら、「仮想通貨=雑所得=高税率」という言説は、二重の意味での誤解を生じさせる可能性があります。
(1)「仮想通貨=雑所得」の誤り
雑所得というと、言葉のイメージとしていかがでしょうか。なんとなく、雑多なイメージがしませんか?読者の皆様が感じられるように、実際のところ、「雑所得」とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得を言います(所得税法35条)
たとえば、銀行預金の利息は利子所得として、源泉分離課税の対象となり、銀行から利息が支払われる際に自動的に15%の税金が控除されることになっています。
給与所得とは、ざっくり言えば給料のことです。このように、それぞれの所得については、所得の原因が名称からはっきりイメージがつくのに対し、「雑所得」はこれらの所得と異なり、分類から漏れたすべての所得を指します。つまり、簡単に言えば、「カテゴリーに分類できない所得」を雑所得と呼んでいるのです。
では、なぜ仮想通貨が雑所得に分類されると言われるのでしょうか。それは、おそらく、仮想通貨の売買が社会一般に浸透していないからです。しばしば雑所得と対比される所得として「事業所得」が挙げられます。
事業所得とは、いわゆる自営業者の営業から生じた所得のことを言います。事業所得に当たる場合、他の所得との損益通算が可能となる点が雑所得と大きく異なります。
この損益通算というのは、ある人が複数の種類の所得を得ているときに、一方の所得で出た損失を他方の所得の黒字から差し引くことができるという仕組みです。
個人の所得税は、全所得を総合して(総合課税といいます)、所得額に応じて税額が計算されるという仕組みを原則としているため、損益通算ができれば、全体として見て所得税を減らすことができるのです。
損益通算は事業所得では可能ですが、雑所得ではできません。つまり、雑所得に分類されると、仮想通貨での取引で多額の損失を被ってしまったとしても、本業で給与をもらっている場合には、やはり給与の額だけの所得があったものとみなされて、相応の所得税を払わないといけなくなってしまいます(驚くべきことに、仮想通貨での損失が本業の年収よりも多くても、税金を支払わないといけないのです。)
ところで、ある所得が雑所得になるか、事業所得になるかは、その所得を生じさせる行為(今回でいうところの仮想通貨の売買)が客観的に職業として行っていると認められるかどうかにより決まります。
仮想通貨の売買は雑所得である、という意見は、あくまで、あなたの仮想通貨の売買が趣味の域を出ないことを前提とした議論です。あなたが、1日の大半を仮想通貨の売買に費やし、そのために必要なPCや帳簿を用意しているのであれば、それは事業といえる可能性があります。したがって、「仮想通貨の売却益=雑所得」というのは、誤解を含んだ言説なのです。